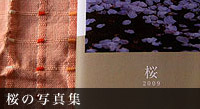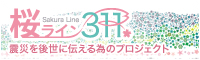法用寺 虎の尾桜
会津五桜
三重塔で知られる法用寺観音堂前にあり、新編会津風土記(文化6年 1806)にも記されている古木です。
縁起書によれば徳溢大師が植えたと言われており、藩政時代には藩主と姫君がよく観桜に来られていたそうです。
根元には古い株が見受けられますが、現木は何代目の桜であるかは不明。

名前の由来は、その形から虎の横たわる姿に見立てた説と、おしべの変化した旗弁が花の中央から出ているところからそう呼ばれるようになったという説があります。
毎年3本の幹から延びる枝に淡紅色の美しい花を咲かせ、 花は八重で薄紅色、非常に珍しい桜です。

法用寺までは集落の細い道を車で登って行きます。
人はまばらで、近所の人でしょうか、境内でまんじゅうを売っています。
4〜5回訪れましたがタイミングが悪いのか、なかなか満開の姿を観る事ができません。
近くにある千歳桜よりも開花は遅い様です。

向かって左方向に進むと、県の重要文化財である三重塔が建っています。これは会津で唯一残存する三重塔です。
また、法用寺にあるケヤキの一本彫りの金剛力士像(こんごうりきしぞう)・観音堂厨子(ずし)や仏壇などは、国の重要文化財に指定されています。

境内には染井吉野が数本、中央には池があります。高台からは会津の風景を見る事ができます。

弁天石(抱き石)
抱きつくと、子宝が授かるといわれています。
弁天石の由来(看板より)
今から凡そ1195年前、大同3年(808)観音堂建立の際、徳溢大師が植えられた、この木(虎の尾桜)の下で大師がうつうつと仮眠された時、妙なる楽の音と共に美しい天女が舞い降りて静かに大師のそばにたたれて、にっこりと笑みをたたえたので、ふしぎに思う中
(われは弁財天なるよ そなたの力となりこの堂塔の助とならん)
と云われ、目覚めてみるとそこにこの石があったので弁天石と名付けこれを北の川のほとりに祀り、もし子のない女はこの石に抱きついて祈りご利益で子が授かったという、その後洪水で流されたのでこの地に復元する。
桜を観ながら文化財を巡るのも良いですね。
撮影日:2007.5.3・2010.5.3・2013.4.29・5.5
法用寺 虎の尾桜 - DATA |
||
【種 類】 | サトザクラ - 樹齢200年 - 町指定天然記念物 - 会津五桜 | |
【住 所】 | 福島県会津美里町大字雀林字三番山下3554 | |
【交 通】 | 電車 | JR東北新幹線郡山駅下車 - 乗り換え - JR磐越西線会津若松駅下車 - 乗り換え - JR只見線会津高田駅 - 車約10分 |
車 | 磐越自動車道新鶴スマートICもしくは会津坂下IC | |
|
Warning: include(navi/navi_fukushima.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/users/2/watarigraphic/web/sakura/houyouji.php on line 167
Warning: include(navi/navi_fukushima.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/users/2/watarigraphic/web/sakura/houyouji.php on line 167
Warning: include(): Failed opening 'navi/navi_fukushima.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/7.4/lib/php') in /home/users/2/watarigraphic/web/sakura/houyouji.php on line 167